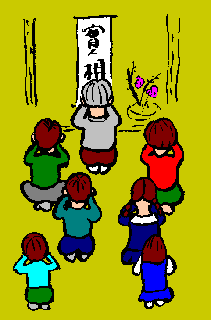
三好 雅則(生長の家本部講師)
<<本文を読む>>
「男は仕事、女は家庭」と決め付け、家庭は妻に任せ、
男は仕事に没頭するいうのが当たり前だった“高度経済成長期”は、
すでに過去のものとなって久しい。
が、未だに、こうした生き方を続けている男性、父親も多い。
「団塊の世代」の末席に属する私も、
「家庭第一主義」を戦後民主主義に毒された“利己的な生き方”であると、
どこかで否定して生きてきた一人だった。
極端な言い方になるが、
ある意味では、
私のこうした「家庭を顧みない心の姿勢」が結局、
それを構成する子供たちへの軽視に、
どこかで繋がっていたのではないかということを、
次女の一件で改めて感じた。
また生長の家で「人間は皆神の子である」と教えられ、
常に相手の神性・仏性を礼拝する生き方をしている“つもり”だったが、
結局、身近な家庭の中で、十分にはそれが表現されていなかったことを反省した。
振り返れば、この次女は幼いころから母の手伝いや姉や兄に頼まれたことを嫌がりもせず
よく引き受ける思いやりのある子だった。
妻が亡くなってから、私と子供達でローテーションを組んでやることにしていた食事の支度も、
長女、長男はクラブ活動で、私も仕事の関係で帰宅が遅いため、
結局、彼女が行うことが多かった。
中学校から空腹を抱えて帰宅し、すぐに食事の支度をする日が続いていたわけだから、
イライラが募のることもあったに違いない。
本人によれば、
「“男言葉”は一種の流行で、なんとなくつかってみただけ。
それ以外、特別の意味はない」
とのことだったが、
“男言葉”は、当時、毎日のように行っていた家事などで溜まったフラストレーションを解消する
“ささやかな方法”だったのだろう。
が、子供の日常生活やその中で感じていることなどを思いやる気持ちがなかったわけではないが、
それまでの私には、それがかなり希薄だったのだと思う。
そのため、上に述べたような次女の日常生活などについて思いやる気持ちが足りなかった。
人間にはさまざまな側面がある。
一個人であると共に、家庭の一員であり、社会、職場、国家、そして地球人類の一員である。
それぞれの立場で、それぞれの役割を十全に生きることが求められるのだが、
それには最も近くにいる人々との関係を除いてはありえない。
谷口清超先生は『伸びゆく日々の言葉』の中でこのように示されている。(同書157ページ)
七月六日 近き人々への愛
<<(前略)子を愛し、部下を愛する者でなくて、
どうして世界を愛し、平和を愛することができるか。
大をなすには、小に徹しなくてはならぬ。
神は大宇宙を一糸乱れず運行されると共に、
極微の世界をも秩序正しく保持し給うのである。(後略)>>
(生長の家相愛会「父親教室」HPの「今月の講義」2002.10公開)